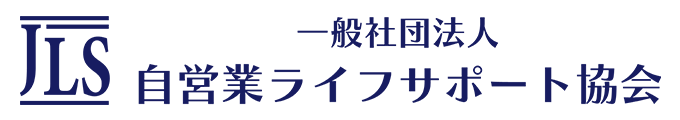個人事業主は病気やケガで仕事ができなくなった場合のリスクが大きいもの😣
有給休暇や傷病手当金などは原則として利用できないため、生活への影響は深刻です。特に、長期間の療養が必要になった時には、収入減や医療費の負担が重なり、事業の継続が困難になることもあります。
万が一の事態に備えて、給付金や保険などの制度を理解しておくことが大切です✨
この記事では、個人事業主が病気になった時に受け取れる可能性のある給付金制度について詳しく解説していきます☝️
個人事業主が病気で働けなくなった時のリスク
個人事業主が病気で働けなくなった場合には、以下のリスクがあります。
- 傷病手当金、雇用保険がない
- 収入ストップによる生活費への影響
会社員は社会保険に加入していますが、個人事業主は国民健康保険に加入しています。
国民健康保険は医療費を一部補助してくれる健康保険制度ではあるものの、社会保険とは異なり傷病手当金を受け取ることができません。
また、病気になり事業の運営が難しくなった場合に、次の仕事を探すまでの生活資金や職業訓練を受ける費用の一部支給といった雇用保険の保障が受けられないことも、デメリットです。
誰でも使える!高額療養費制度
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度。
全ての人が安心して医療を受けられる社会を維持し、世代間の公平性を保つため、所得に応じた限度額が定められています。
所得が増えるほど、医療費の負担も増えてしまいます。
個人事業主も活用できる!病気になった時の給付金制度
個人事業主は、傷病手当金や雇用保険による保障は受けられないものの、病気になった時に利用できる制度が用意されています。
ここからは、個人事業主が利用できる3つの給付金制度について解説していきます。
➀労災保険の特別加入
労災保険は労働者を守るための制度で、仕事中や通勤中に発生した事故や職業病になった場合に治療費や休業補償、障害補償などを受けられる保険です。個人事業主は労働者ではなく事業主にあたることから、原則として労災保険に加入できません。しかし、労災保険の特別加入によって、一部の業種・職種に該当する個人事業主も労災保険に加入できます。
②自立支援医療制度
心と体の障害を軽減または取り除くための治療にかかった費用を軽減するための制度です。精神疾患を罹患し精神病院に通院している人や、更生医療を受けている人などが対象となります。
③障害基礎年金
国民年金に加入している間に障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合に支給される年金です。
個人事業主が給付金以外の備えとして使える保険・制度
労災保険の特別加入や自立支援医療制度、障害基礎年金などの給付金制度は用意されていますが、生活費や医療費を賄えるかどうか不安に感じる人もいるでしょう。
ここからは、給付金以外の備えとして使える保険や制度についても紹介します。
- 医療保険
病気やケガになった際の治療費や入院・手術にかかる費用をカバーできる保険
民間の医療保険に加入しておけば、入院や手術にかかる費用を賄うことが可能です。 基本的には医療費負担を補うものであり、収入を補償するための保険ではないので注意してください。
- 就業不能保険
病気やケガが原因で長期間にわたり働けなくなってしまい、収入が減少した時のために備える保険
働けなくなってから60日間の待機期間があり、その後給付金を受け取ることができます。就業不能保険に加入していれば、傷病手当金を受給できなくても収入がゼロになることはありません。
- 所得補償保険
病気やケガなどが原因で万が一働けなくなってしまった際に、所得を保障するための保険
就業不能保険と同じく、収入の減少リスクに備えるための保険ですが、基本的には生命保険会社が就業不能保険、損害保険会社が所得補償保険として提供しています。また、就業不能保険は60歳や70歳までと長期にわたって給付金を受け取ることが可能ですが、所得補償保険は1~5年間と比較的短めに設定されていることが大きな特徴です。
- 個人年金保険
老後の生活資金に備えるために活用できる私的年金のひとつ
公的年金を補完するためのものであり、保険期間・年金額などは各商品によって異なります。
- 小規模企業共済
中小企業の経営者や個人事業主が将来の備えとして活用できる制度
小規模企業共済によって掛金を積み立てておくことで、退職金として受け取れます。毎月の掛金は1,000円~7万円まで500円単位で設定でき、加入後に増減させることも可能です。また、全額課税対象所得から控除でき、節税効果が得られることもメリットといえます。ただし、掛金納付月数が240カ月(20年)未満で任意解約をすると、受け取れる共済金が掛金の合計金額を下回ってしまい、元本割れを起こしてしまうので注意が必要です。
- 所得税・住民税の納税猶予
期限内に所得税・住民税を納めるのが困難な場合は、国税または市区町村の猶予制度を活用してください。
国税の猶予制度は、納税により事業継続や生活が困難になってしまう場合や、災害などの被害に遭った場合に、税務署へ申請することで原則1年以内は納税が猶予されます。
給付金を受け取るまでの期間は?
給付金制度は、申請から支給されるまでに数カ月かかることを想定しておくことが大切です。
障害基礎年金の場合は審査に3カ月程度、審査に通っても実際に受給されるまで1カ月半近くかかる場合もあり、申請から4~5カ月後に支給される可能性もあります。
また、労災保険の特別加入でも、給付されるまでに1カ月以上かかってしまうケースもあります。
病気で働けなくなった時にすぐ使えるお金が支給されるわけではないため、空白期間の生活資金をどのように確保するかが重要です。
生活費をカバーする手段として、就業不能保険や所得補償保険、小規模企業共済の貸付制度など民間の備えが必要となります。
公的給付と民間の備えをうまく活用しつつ、早めに準備することが大切です。
個人事業主が病気で働けなくなる前に備えるべきこと
- 事業と生活の両方を補えるだけの資金を確保しておく
病気で働けなくなった時のために、事業面に加えて生活資金も補えるだけの資金を確保しておくことが重要です。
働けなくなると事業をストップせざるを得ない状況に陥り、仕事ができない状態が続けば収入はゼロです。また、運転資金がなくなれば、事業の継続が困難になります。数カ月~1年分程度は、事業の運転資金を確保しておくと安心です。
なお、事業の運転資金に加え、生活費も確保しておかないといけません。 会社員であれば生活費の半年程度が目安となりますが、公的保障が手薄な個人事業主は1~2年分は用意しておいてください。
- 経営状況や今後の手続きに関して家族・専門家と連携しておく
働けなくなった場合でも、経営状況をすぐに把握できたり、給付金の申請・手続きなどをすぐ行えるようにしたりするために、事前に家族や専門家と連携しておいてください。
例えば、税理士と連携を取っておけば、税務申告を代行してもらったり、所得税・住民税の猶予制度を利用したい場合に相談したりできます。
また、家族と連携が取れていれば、自分が仕事をできなくても家族に事業を引き継いでもらうことも可能です。
個人事業主が病気で働けなくなった場合の確定申告
個人事業主が病気になり働けなくなると収入がゼロになってしまうことから、「確定申告は不要」と考える人もいるでしょう。年間所得が48万円以下の場合や副業分の所得が20万円以下なら、確定申告を行う必要はありません。
しかし、病気などが原因で売上げがなかったとしても、確定申告をすることで損益通算や純損失の繰り越し・繰り戻しなどを利用できます。
住民税を申告していなければ国民健康保険料が高くなったり各種証明書の発行ができなくなったりするため、確定申告するほうが良いかもしれません。
まとめ
病気で働けなくなった時のために早めの備えが大切!
個人事業主が病気で働けなくなった場合、会社員や公務員よりも公的保障が手薄なため、すぐに収入が減ってしまう可能性が高いです。
そこで、私たち自営業ライフサポート協会では、個人事業主の方専用で、社会保険に加入できるサポートを提供しています。
当協会に加入すれば、高額療養費制度の負担を抑えられて、公的保障を受けることができます!
ご興味のある方は、ぜひ一度10秒診断をお試しください😊